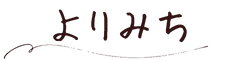クライアントと打ち合わせをしたはずなのに、いざ進めてみると「やっぱりちょっと違うかも」「もう少しこうしてほしい」気づいたときには仕様が大きく変わっていた——。
そんなふうに、あとから仕様変更が重なって困った経験はありませんか?
この記事では、クライアントの要望がうまく引き出せないときにどう対処すればいいか、私の実体験をもとにお伝えします。
私は10年以上、化粧品の商品開発に携わりながら、何度も“あとから変わる問題”に直面してきました。
現場で失敗と試行錯誤を繰り返す中で見えてきたのは、最初に方向性を具体化することの大切さです。
この記事を読むことで、打ち合わせ後のすれ違いを減らし、よりスムーズにプロジェクトを進めるためのヒントが見つかるはずです。
最初からうまくできなくて当たり前
振り返ってみれば、私自身も最初からうまくできていたわけではありません。
むしろ要望に振り回されて、悩むことのほうが多かったです。
「もっと早く言ってくれればよかったのに…」と心の中で思いながら、対応していました。
何度も同じようなやりとりを繰り返す中で、最初に大枠の方向性をつかめれば、後のすれ違いを減らせると気づきました。
そこから少しずつ、イメージのズレを防ぐ工夫を意識するようになったのです。
「やっぱりちょっと違うかも」を避けるためにできる2つの工夫
イメージのズレを防ぐには、打ち合わせの場での工夫が欠かせません。
ここでは、私が実際の開発現場で試して効果を感じた2つの方法をご紹介します。どちらも特別な技術は必要なく、今日から取り入れられるものです。
視覚的なサンプルを活用する
イメージのズレを防ぐために有効だったのが、“視覚的なサンプル”を活用することです。
私が関わっていた化粧品開発の現場では、仕上がりイメージを言葉だけで共有するのがとても難しいものでした。
そんなときは、いくつかの試作品を並べて「Aの使用感、Bの発色、仕上がりはマットな質感で」といった具合に要素を分解しながら、一緒に選んでもらうことを心がけていました。
サンプルを用意できないときには、雑誌やネットの画像を見ながら会話を重ねてイメージを引き出します。
大切なのは、「こんな感じですか?」とこちらから具体的な例を出して、相手に考えるきっかけをつくること。
相手の頭の中にあるイメージを、少しずつ輪郭のある形にしていくことを目指しました。
イメージがまとまらないときは一度持ち帰ってもらう
話し合いの中でイメージがどうしても曖昧なまま進みそうなときは、
「一度整理してから改めて方向性を決めませんか?」とこちらから立ち止まる提案をするのもひとつの手です。
早く決めて試作に進めたい気持ちはお互いにあるものの、曖昧なまま進めるほうが結果的に遠回りになることもあります。
「決めきれない=悪いこと」ではないと捉えて、対話のプロセスを大切にすることもズレを防ぐ対処のひとつです。
実現可能かどうかを見極める視点も忘れずに
要望をうまく引き出せたとしても、実現が難しい場合は「できません」と伝えなければいけません。
そのときにただ、「無理です」と言ってしまうと関係性にヒビが入ることも。
だからこそ、「なぜ出来ないのか」「他の代替案はあるか」をきちんと整理して伝えることが大切です。
また、表面上は実現できそうに見えても、後々トラブルになりそうな要素がないかを見極める視点も重要です。
こういった視点は、経験が浅いときに判断するのは難しいので、打ち合わせをするときに上司やベテランの先輩についてもらうことがおすすめです。
その時に、どんな質問をしていたのか、何を確認していたのかをメモしておくことで、少しづつ自分だけでも対応できるようになってきます。
さらに技術的・実務的にどうかだけでなく、「その要望は開発背景・趣旨とあっているのか?」という視点を持つことで、よりスムーズな進行につながります。
まとめ
クライアントの要望をうまく引き出すには、最初から完璧を目指すのではなく、一緒に見えていないものを見える化するプロセスが大切です。
サンプルや具体例を使ってイメージを共有し、要望の背景にある「意図」にも目を向ける。
不安なときは、上司やベテランの先輩に手を貸してもらいましょう。
その時にどんな質問をしていたのか、何を確認していたのかをメモしておくことで少しづつ自分だけでも対応できるようになってきます。
そうした小さな工夫の積み重ねが、「やっぱりちょっと違うかも」を防ぐことにつながるのだと、私自身の経験から感じています。