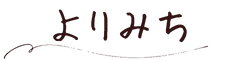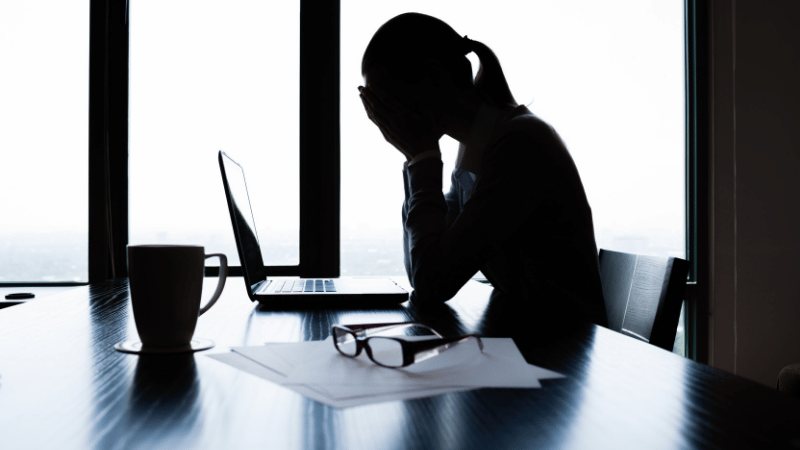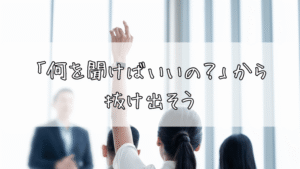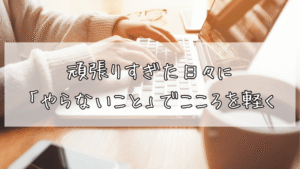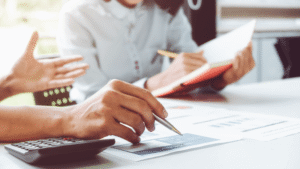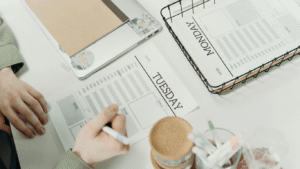「何度も教えたのに、なかなか実行してもらえない」
「自分の伝え方が悪いのかもしれない」
新人教育をしていると、こんなふうに落ち込むことはありませんか?
私も育成担当を頼まれるたびに、同じ悩みを抱えていました。
何人もの人に教える中で、完璧に教えようとしなくていいということに気づきました。
この記事では、新人教育に悩んだ経験から学んだ3つのポイントを紹介します。
少しでも心が軽くなり、「じゃあこうしてみよう」と思えるヒントになれば嬉しいです。
上手に伝えられなくてもいい
教えたことをその通りにやってもらえないことは、何度もありました。
そのたびに「自分の伝え方が悪いのか」と落ち込みましたが、次第に考えが変わっていきました。
結果的に仕事が進んでいれば、それで十分。
受け取る側に「受け取る準備」がなければ、いくら頑張って伝えても響かないことがあります。
だからこそ、教える側が必要以上に落ち込む必要はないのだと思うようになりました。
 ゆう
ゆう新人さんは業務以外に会社の中で使われる共通言語も覚える必要があるので、教えるのが難しいと感じてました。
失敗からしか学べないこともある
あるとき新人さんからこんな言葉を聞きました。
「話では注意点をわかっているつもりでした。でも、実際に自分で失敗してみてようやく“やってはいけないこと”だと理解できました。」
その言葉を聞いたとき、「あぁ、結局は体験しないと分からないこともあるんだ」と納得しました。
それ以来、あえて失敗をさせることも育成の一部だと思うようになりました。
もちろんフォローは必要ですが、失敗を通じてこそ身につく学びがあるのだと感じました。
伝える方法を変えてみる
同じ内容を何度も質問されることもありました。
最初は「なんで覚えてくれないんだろう」と思いましたが、試しに伝え方を変えてみることに。
口頭だけでなく、メールやチャットで同じ内容を送るようにしました。
すると、相手が後から見返せるようになり、理解度も上がったのです。
伝え方は一つじゃありません。
自分とはタイプの違う同僚から話をしてもらったこともあります。
相手に合わせてフォロー方法を変えることで、少しずつ「伝わる」形を見つけられるようになりました。
まとめ
新人教育は「思い通りにいかない」のが前提です。
- 教えたことを実行してもらえなくても落ち込まない
- 失敗を経験しながら学んでもらう
- 伝え方を変えて工夫してみる
この3つを意識することで、私自身も気持ちが楽になり、新人との関わり方が前向きになりました。
育成担当だからといって、最初から完璧にできる必要はありません。
うまくいかないな、とつらくなるときは自分の感情が入りすぎているかもしれません。
教える相手に対して必要以上に期待していないか振り返ってみましょう。