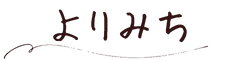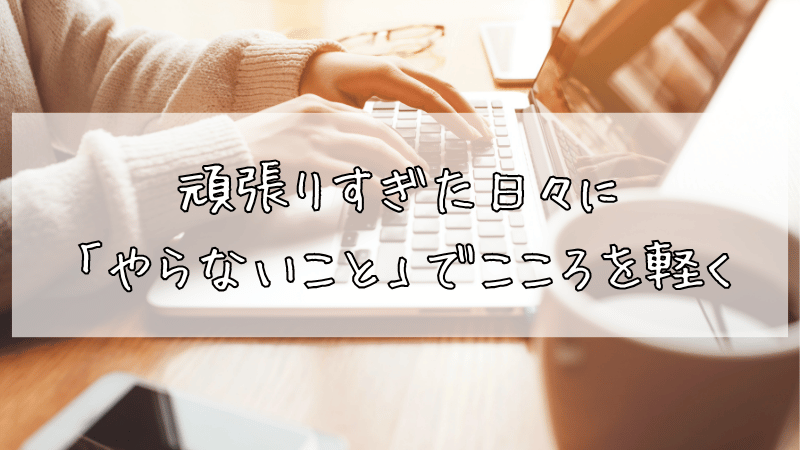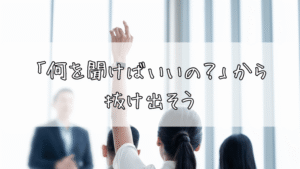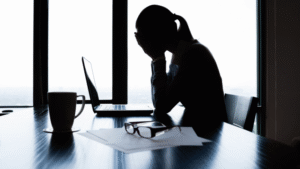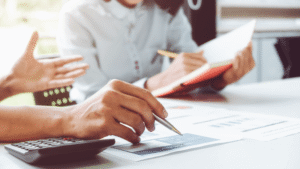「毎日やることが多すぎて時間が足りない」
「ToDoリストを作っても全然減らない」
こんな状況で困っていませんか?
気づけば残業ばかりで、家に帰っても頭の中は仕事のことでいっぱい。
「効率化しなきゃ」と焦るほど、やることリストが増えていく——。
私も会社員として働いていた頃、同じような悩みを抱えていました。
ToDoリストを作っても、就業時間後にならないと手が付けられない日々が続いていたのです。
そんなときに効果があったのが、「やらないことリスト」を作るという方法。
この記事では、仕事の効率を上げたい人や毎日の忙しさに追われている人に向けて
やらないことリストの作り方と続けるコツをご紹介します。
やらないことリストを作る理由
ToDoリストは「やることを増やす」仕組みですが、「やらないことを決める」ことも大切です。
やらないことを明確にすると、自分が集中すべき仕事にエネルギーを使えるというメリットがあります。
私自身、時間の使い方を見直す中で気づいたのは、
「自分がやらなくてもいい仕事」に意外と多くの時間をとられていたということでした。
例えば、私がまだ役職がない一般社員だったころの話です。
上司が毎回ミーティングの日程調整を自分で行っていたのを見て、
「それ、上司がやらなくてもいい仕事では?」
「その調整に時間を使うより他に優先すべきことがあるのでは?」と思ったことがあります。
そのときは思い切って上司に「任せてもらえませんか?」と提案しました。
この経験から、仕事の役割によってその人しか出来ない仕事を見極めることが限られた時間を有効に使うための工夫なんだと実感しました。
やらないことリストの作り方3ステップ
ステップ1 時間を奪っていることを書き出す
普段の仕事の中でこちらの2つに当てはまる作業を洗い出します。
- 誰がやっても結果が変わらない作業
- かけている時間に対して成果が見合わないこと
例えばこんなことです。
- 備品の在庫管理と発注作業
- すべての会議に参加する
- 完璧な資料作りにこだわる
- 長時間の残業
1日のなかで時間をかけた割に進捗が悪かった作業はありましたか?
「なぜ進まなかったのか?」を掘り下げてみるとやらなくてもいいことが見えてきます。
私自身の例で言えば、「資料の装飾に時間をかけること」でした。
見やすさは大切ですが、デザインにこだわりすぎていたのです。
”伝わる資料で十分”と気づいてからは、時間の使い方がぐっと楽になりました。
ステップ2 なくても困らないことを見つける
リストの中から「やめても問題ない」ことを選びます。
自分で決められること(例えば「資料の装飾に時間をかけない」)から試してみましょう。
最初は抵抗があるかもしれませんが、やってみて不便を感じたら戻せばいいだけです。
一度手放してみることで、必要な仕事だけが残ります。
一方、自分の判断だけではやめられない作業、例えば備品管理や発注のように「気づいた人が回している仕事」は上司に相談してみるのがおすすめです。
「どうすれば仕組みとして回せるか?」を一緒に考えることで、チーム全体の効率化にもつながります。
ステップ3 やめるルールを決める
「やらないこと」を行動ルールとして明文化します。
例えば
- 夜はメールを見ない
- 会議の出席は目的が明確なものだけ
- 資料は”伝わること”を目的に作成する
私は特に「夜はメールを見ない」ことを徹底していました。
スマホに通知がくると確認して、ついパソコンを開いて仕事を始めてしまうこともありました。
結果、頭がさえて寝付けなくなり翌朝まで疲れが残ったのです。
思い切って「夜は見ない」と決めてからは、睡眠の質も上がり翌日の集中力もぐっと高まりました。
やらないことリストを続けるコツ
それはこちらの3つです。
- 完璧を目指さない:リストは日々の仕事や状況にあわせましょう。
- チームで共有する:上司や部下に伝えておくと理解が得られやすくなります。
- ”空いた時間”を大切に:自分のために使いましょう。
「やらないことリスト」は怠けるためのリストではありません。
自分のやるべきことに集中するための大切な選択です。
まとめ
仕事に追われて時間が足りないと感じたら、やることを増やすよりもやらないことを決めることから始めてみてください。
- 自分がやらなくてもいい仕事を手放す
- 時間を奪う週間を減らす
- 「やらない」を行動ルールとして決める
この3つを意識するだけで、仕事もこころも少しずつ整ってきます。
やらないことを決めるようになってから、やるべきことに迷う時間が減り、気持ちにも余裕が生まれました。やらないことを決めるのは、自分を守るための選択。
今日から5分だけ時間を取って「やらないこと」を3つ書き出してみませんか?
仕事の整理だけでなく、こころの整理も大切です。
人間関係に疲れたときや、気持ちを立て直したいときはこちらの記事もおすすめです。