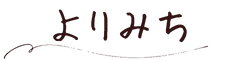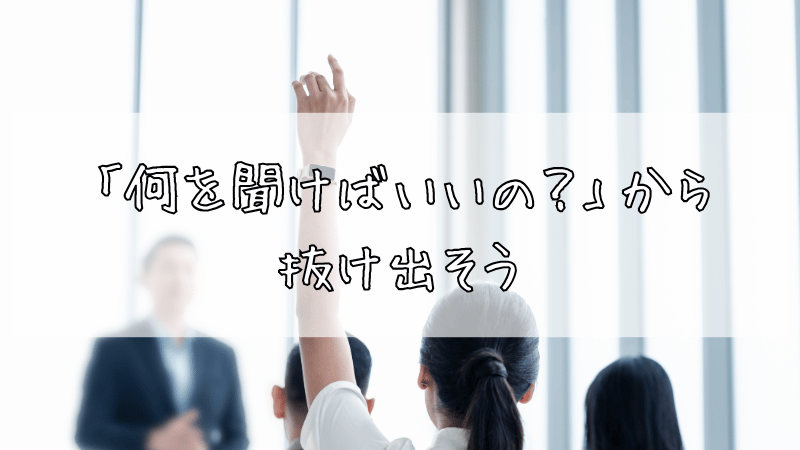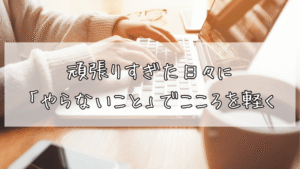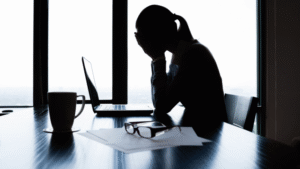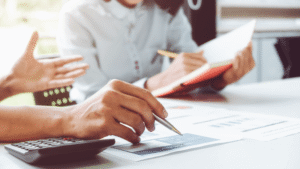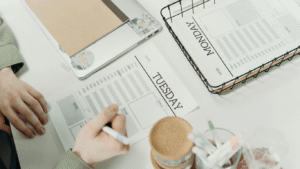質問が出てこないのは、理解力が足りないからではありません。
相手の話を「なるほど、そうなんだ!」とそのまま受け入れていませんか?
質問は「それって本当?」「どうしてそうなったのだろう?」「何が原因なんだろう?」
といった疑問がきっかけです。
そうは言っても疑問が浮かばないから困っているのに・・・と思ったあなたへ
質問力はセンスではなく、練習することで鍛えられます。
この記事では、打ち合わせや会議で「質問が出てこない」と悩む人に向けて
すぐに実践できる質問力トレーニングをご紹介します。
質問力を鍛える2つの考え方
質問が出てこないときは、2つの方向から考えてみると効果的です。
- あいまいな言葉を深堀りする
- 立場を変えて広げる
それぞれを使い分けることで、質問が自然と浮かぶようになります。
1.あいまいな言葉を深堀りする│具体化の質問
深堀りする、というと難しそうに聞こえますが「具体的にしていく」というイメージのほうが近いです。
ポイントは、あいまいな言葉を意識することです。
たとえばクライアントが「もっと使いやすい商品にしたい」と言ったとします。
ですが”使いやすい”という言葉にはさまざまな意味が含まれています。
- 手順が少ない
- 軽くて持ち運びしやすい
- 他のアイテムと一緒に使える
こういった複数の意味が含まれる言葉は疑問のきっかけになります。
話の流れから「使いやすい」という言葉の前提がわからないときは質問のチャンスです。
「”使いやすい”というのは、どんな場面を想定していますか?」
「どの点が今の仕様で使いづらいと感じていますか?」
「それはどのユーザー層にとって重要だと思いますか?」
以上のような質問によって「もっと使いやすい商品にしたい」という要望に対して話を深めることが出来ます。
トレーニング法
メールや資料を作るとき、具体的な表現を心がけましょう。
複数の意味を含むような文脈、抽象的な表現をしていないかチェックするところから始めてみます。
2.立場を変えて広げる│多角的な質問
話を広げるには別の角度から見る意識を持ってみましょう。
同じ情報でも、立場を変えると意見が変わります。
たとえば「新しい機能を追加したい」という話をしていたとします。
ここで部署によってどんな考えになるのか想像してみます。
- 開発担当なら:コストや工数が増えるリスクを考える
- 営業担当なら:差別化できるチャンスと捉える
- 使う人なら:操作が複雑にならないか気にする
このように他の立場になって考えることが、質問を生むきっかけになります。
「使う人の立場から見て、その機能があることのメリットはありますか?」
「コストの目標はいくらですか?」
「その機能は他社にはないものですか?」
部内での打ち合わせのように立場が同じ人の集まりの時は、違う立場での考えによって会話の質がぐっと上がります。
トレーニング法
普段から他部署の人とコニュニケーションを取ってみましょう。
様々な立場を理解することで質問の引き出しを増やすことが出来ます。
まとめ│質問力は「視点」で磨かれる
質問力とは相手の考えを深めたり・広げたりする力です。
「質問が出てこない」と感じたときは、まずこの2つの視点を意識してみてください。
- あいまいな言葉をきっかけに具体化する
- 他の立場になって広げてみる
質問力は、経験よりも思考の習慣で育つスキルです。
今日の打ち合わせからひとつ実践してみませんか?
質問によってイメージを具体化する手法についてはこちらの記事も参考になると思います。